フライフィッシングの「足回り」:リバーフィッシング編
アングラーが両手を使ってロッド&リール、フライラインを操作するフライフィッシングですが、一回一回のキャスティングやフィッシング動作に大事な「手返し」はもちろん、体重移動を行ったり、ポジション変更や移動を重ねることで「足回り」も大変重要な要素になっています。

足場が整地されているエリアや足場に難が無いフィールドではあまり気にすることがありませんが、より管理されていない自然なフィールドに出向く場合はもちろん、自然の脅威もあるアドベンチャーへ遠征する場合はさらに気を付けることがたくさんあります。
- 2025.5.28: トレッキングポールや靴の履き分けについて追記
- 2025.5.7: 初回アップ
水辺歩行の特殊な点
川原へ至る傾斜地・・・坂・斜面・崖

人間にとって活動しやすい道路や駐車スペース、林道や土手は洪水から守る目的もあって、水辺よりも高い位置になっています。高い地形から低い地形の川原へエントリーするルートは傾斜地を経ることになります。
水辺利用者の数が多くて、滑らかなルートになっている場合もあれば、滅多に利用者がこないために険しいままになっている場所もあれば、補助のロープを利用者がセットしてくれている場所もあれば、自らがロープワークをマスターしていないと上り下りできない崖のような危険な場所もあります。
地面

普段の生活で歩き慣れている地面とは違い、整地されていない水辺には大小様々な石が無数に転がっていたり、水の勢いで削られた穴が空いていたり、穴の上に様々な漂流物が覆い被さって足を踏み入れると重さで崩落したり・・・。それも両手が空いている状態でも歩きづらい地面を片手に釣竿を持ってポイント移動を急ぐため、慣れていてもある程度の時間を通じて精神的な疲労が溜まることになります。
また常に水が出る川原は地面が濡れていたり、伏流水が流れ出ていたり、必ず「濡れる」場所が存在します。
底質

川原には水の力でどこからから運ばれてきた岩が並び、強い流れで削られて丸くなった石が堆積しています。「ぐらつく岩」や「転がる石」が一定数あることはもちろん、湿度が高い環境のため、苔や藻類が岩や石の上に生えることで非常に滑りやすくなっている場合もあります。
水深

スニーカーでクリアーできる、くるぶし程度の水深もあれば、膝下まで立ち込まないと移動できない場所や渡れない浅瀬もあります。さらに腰までウェーディングしないと進めない渓流や小規模の本流があります。
山岳地形では、最も抉れた場所を川が流れているため、例えスタート時には大した流れに見えない源流であっても、場所に応じて溺れてしまうような深みがあったりします。また本流に至っては、転倒時には安全確保の水泳を覚悟しなければならないような胸まで深い場所もあります。
水圧

くるぶし程度の水深ではほとんど感じることの無い水圧ですが、膝下まで川へ入れば流れに足の表面積が押されてかなりの水圧を横から受けることになります。膝上まで川へ入ると、くるぶしに続き膝という重要な稼働パーツも水中に入るため、水圧の影響はより大きくなります。腰より上まで水中に入ると体幹全体へ水圧を受けるため、流れの強さによっては全く進めなくなってしまうこともあります。
さらに流れが速ければ速いほど、水量が増えれば増えるほど、コントロール性は落ちていきます。
浮力
さらに腰まで川へ入れば下半身の稼働部全てが水中に入るために動きづらさが一気に悪化するだけでなく、浮力のために体重が軽くなるために、足の裏のグリップ力も低下します。
水温
川の水温は体温よりも遥かに低く、浸水しない素材のウェーダーを履いていたとしても時間経過とともに間接的に熱を奪われているために体温も下がっていきます。人間の体は手足が冷えると優先的に血流を心臓などを守るために身体の中央へ回してしまうめ、足の筋肉が動きづらくなっていきます。
これらは自然条件や河川環境で変化する
これら水辺の足回りに影響する条件は、天候などの自然条件や河川環境によって常に変化しています。春先には水が適量で滑らずに歩きやすかった川が、GW頃には水量が増えて苔が増えて滑りやすくなったりします。
また、昼過ぎまでは水量が少なかった川が、上流側の支流のどこかで放水が行われたり、源流部の山岳地帯で大雨が降ったために突然水量が増えたりもします。水中の流れの方向も変化するため、足を取られやすくなったりもします。
水辺で起きるハプニング
ふらつき
足場が良くない地面を歩行する際にふらつくことは当たり前かと思われるかもしれません。しかし、日常生活でふらつくことがない人でもふらつくことがあるのが装備品を持った状態での川原歩行です。手ぶらで歩行する状態のコントロール性能が100%だとすると、上記の条件や自分自身の疲労が原因でそれが50%や30%にもなり得ることを理解しましょう。
転倒
ふらつくだけでなく、「滑り」「つまずき」「踏み外し」の3大要因で足運びに失敗した時に体勢が崩れてコントロールを失ってしまう状態、それが転倒です。
滑り
滑る底質や浮力が原因で足の裏のグリップが効かなくなった時に発生します。
つまずき
陸上・水中の障害物や柔らかい底質などに足を取られたり、自分が足元に落としたフライラインなどで足を引っ掛けたり、ランディングネットなど装備品を岩に引っ掛けたりした時に発生します。
また疲れや冷えが原因で脚力が低下した時に、十分に膝が曲がらず足が持ち上がらないことでも発生します。
踏み外し
足場が思ったよりも軟らかく崩れたり、浮石(動く石)に乗ってしまったり、水中の傾斜を読み違えることで踏み外しが発生します。また、濁りや反射により水中が見えづらく、足場の確認が難しい場面では特に注意が必要です。膝以上の水深では流れの抵抗も加わり、踏み外しからの転倒リスクが高まります。
衝撃と落水
川の中で転倒した場合、そのまま衝撃と落水の2つのダメージを受けることになります。硬い岩に身体をぶつけた場合、痛みで動きが取りづらくなります。落水した場合はバランスのリカバリーに失敗することで、さらに転倒したり浸水することで二次的なトラブルにつながります。
浸水
水抜けしないウェアを着用している場合、中へ水が入ってくることで重量が増し動きづらくなり、またピッタリとしていない衣類の場合は水圧を受けることになります。
流され
体勢が整っていない場合、姿勢によっては身体全体が水中で水圧を受けて滑り出すことで、流される状態となります。
溺れ
流されてもすぐにリカバリーできる時、人間は落ち着いて対処できますが、踏ん張りが効かない状態で体のコントロールを完全に失った状態になることで溺れている状態になります。流れに逆らわず掴まることができる岩や倒木、浅瀬を目指してリカバリーを行います。
足回りに求められる要素
自分の脚力を知り、ふらつきや転倒を未然に防ぎ、落水時に流されず、溺れた時に泳ぎやすい服装や装備が最も足回りで安全を確保できます。

グリップ
一歩一歩の確実性は足の裏のグリップ力に関わっています。川辺の場合は衝撃を和らげるクッション性だけでなく、地面や底質にあった靴底が求められます。
脚力と水圧のバランス
体力とスタミナには個人差がありますが、自分の脚力やグリップに見合った水圧や活動時間を知っておくことが大切です。
浮力と体重のバランス
水深がある水中では浮力が増すほど体重が減っていき、グリップ力が低下していきます。
防水トレッキングシューズ
水深・・・くるぶしまで
水たまりが多いエリアや、くるぶし程度の水深の多いフィールドまでは、トレッキングや野外活動で履くようなシューズでカバーできます。
水に浸かると緩むことが多いので、あらかじめ厚手の登山用ソックスを履いておきます。源流などで水辺へのエントリーまで歩く距離が長い場合、トレッキングシューズとウェーディングシューズ両方持っていくと安心です。
ニーハイブーツ(ニーブーツ)
水深・・・膝下まで
膝下の水深まで水中へ入らないと移動できない、自然渓流を利用したエリアや漁協管理河川のようなフィールドでは、最低限でもニーハイブーツが必要となります。水温が冷たい季節は厚手のソックスを履いておきます。
ウェーディングシューズ

水深・・・膝上以上
本格的に水中を歩く場合、足と足首を守りつつ、滑る底質に対するグリップ力を発揮させるためのウェーディングシューズが必須となります。
フェルトソール
最も一般的かつ軽量なのがフェルトソールのシューズです。苔のついた丸石が多い場所や滑らかな岩盤、植物の根っこなど、摩擦で滑り止めしないと歩けない場所では最も歩きやすいソールとなります。
ラバーソール
フィールドによっては、川から菌類や微生物、外来植物の種などを拾ってしまうフェルトソールが禁止されており、その場合はラバーソール一択となります。ビブラムやミシェランなど、登山靴などでも使われる高いグリップ力を発揮するラバーソールが出ています。
また汽水域やソルトの釣りで底質が貝殻や泥岩、砂やサンゴなどの場合は、ラバーソールの方がグリップが高く、足抜けも良くなります。
変換式ソール
複数のシューズを履き分けるのが面倒だったり、荷物を増やせない場合、地面や底質に合わせてソールを変換しながら歩くことができるモデルもKorkersより提供されています。
フェルトスパイク
フェルトソールに金属製のスパイクを装着したものです。硬い底質で滑りやすい地面が多い、防波堤や磯などで一般的に使われていますが重量が嵩むので、これらの地形に隣接した汽水域や河口部で釣りをする時に使います。
ウェーディングソックス: ウェットとドライ
素足とウェーディングシューズの間の隙間を無くし、足を保温するのがウェーディングソックスです。
ウェットソックス(ダビングソックス、マリンソックス)
長時間水中に足を付けたままにしない場合や、水温が高いフィールドで使います。ネオプレーンやクロロプレーンといった発泡素材で保温性があるものを選びます。
ドライソックス
長時間水中に足を付けたままになる場合や、水温が低いフィールドで使います。裾まで水が浸水しませんが、それ以上になると中に水が入ってくるので、冷たい水中で深くウェーディングする際は一度水を入れて体温で温めます。
ウェーディングウェア: ゲーター・ウェーダー・ウェットスーツ・ドライスーツ
ゲーター
膝や膝下の保護・保温のために着用するのがゲーターです。登山道や林道などを長距離歩いて川原へアプローチするような場合はソックス部分の消耗が激しいのでゲーターとソックス別々のものがおすすめです。
ソックスとゲーターが一体化していてフィット感に優れているのがウェットゲーター。
ウェーダー
シューズ&ソックス、さらにゲーターを着用した状態よりも機動力は落ちますが、中が濡れないことで保温効果が高いのがウェーダーです。足の可動範囲が大きくできる、ストッキングタイプ(ソックスと一体化)のものを選びます。ただし流れに対して下流側へ転倒した時にはウェーダーの上から浸水してくるため、注意が必要です。
透湿素材のウェーダー
気温が高い季節に使います。
気温も水温も低い時に使うネオプレーン・クロロプレーンのウェーダー。
ウェットスーツ
初めから濡れる前提で作られ、ネオプレーン素材で保温力も高く、身体にフィットしているのでコンプレッション・タイツの役割も果たし、水圧に対しても動きやすいため、転倒して浸水した時や流された時でも安全に使えるのがウェットスーツです。カヤック用に肩や腕の可動部分が広く、膝などが補強してあるものを選びます。
パドリングジョン
肩の可動部分が広く、フィッシングだけでなく沢登りでも動きやすくなっています。初めから中に水が浸水することで、流された時でも安全にリカバリーを行うことができます。
雨の日や水中を泳ぐような場所を想定する場合は、セットのフルジップシャツ(ダイビングジャケット)も装備します。
ドライスーツ
水温が低い季節に落水しても安全リカバリーすることができるスーツです。
※長時間の低水温には適していませんので、リカバリーしてください
ウェーディングスタッフ
携帯しやすく転倒を予防するための専用の「杖」。
フローティングベスト
泳ぎに自信の無い方は、いざという時のためにフローティングベストの着用がおすすめです。カヤック用・カヤックフィッシング用のものは動きやすく収納ポケットもあります。
その他、足回りを向上させる工夫
コンプレッション・タイツ
筋肉を補完して、長時間の歩行運動でも疲労を軽減してくれるのがコンプレッション・タイツです。ニーブーツやゲーター、ウェーダーの下に着用します。ウェットスーツの場合は着用しません。
セミオート・フライリール
足元でトラブルを起こすことがしばしば発生するのが余分なフライライン。ロッドを持つ手のレバー操作で素早く巻き取ってしまえるセミオート・フライリールで足元スッキリ。
超軽量ランディングネット
足元のフライラインと同様に移動中にバランスを崩す原因になるのが重たいランディングネット。アルミニウム・フレームのものは200g級で、ネオジム磁石を使ったマグネットリリースと組み合わせることで軽快に動き回ることができます。
トレッキングポール
水辺までの移動距離が長い場合、比較的に浅い場所を多く歩く予定の場合は、トレッキングポールを使うと体にも楽です。
装備のコンパクト・軽量化
必要な分だけ携行するチェストパックなどを使い、携行品の重量を落とすことで機動力や運動性を向上させ、疲労を軽減させることができます。
健康管理
ふらつきや転倒は物理的な要因だけでなく、身体的な要因や精神的な要因でも発生しやすくなります。十分な睡眠と疲労回復は身体能力を維持するだけでなく、集中力やトラブル発生時のメンタルヘルスにも直結します。無理をしない行動こそ事故を未然に防ぎます。
関節痛や筋肉痛の軽減
源流や長い林道の歩行で関節が痛むと行動に大きな制限がかかります。ロキソニンSには眠くなる成分や胃を痛める物質が入っていないため、アドベンチャー環境でも使いやすくなっています。
※ご使用には医師の相談を受けてください
筋肉が痺れたり足が攣った時に軽減してくれるのが、ツムラ漢方薬68「芍薬甘草湯」です。
まとめと続き
その他、足回りに役立つものを発見次第、追記します。
この記事のメンバー
参考資料
厚生労働省「転倒の種類」
この記事のディスカッションに参加する | Join the Discussion
東京フライフィッシング&カントリークラブのFacebook グループ「Friends Lobby」ではメンバー以外の方とのディスカッションも行っています。気になる情報や質問などはこちらまで!




























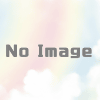




![【入門】とても簡単!フライフィッシングを始めよう[初心者向け解説] 【入門】とても簡単!フライフィッシングを始めよう[初心者向け解説]](https://tokyoflyfishing.com/wp-content/uploads/2023/12/20230628-1-3-100x100.jpg)





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません